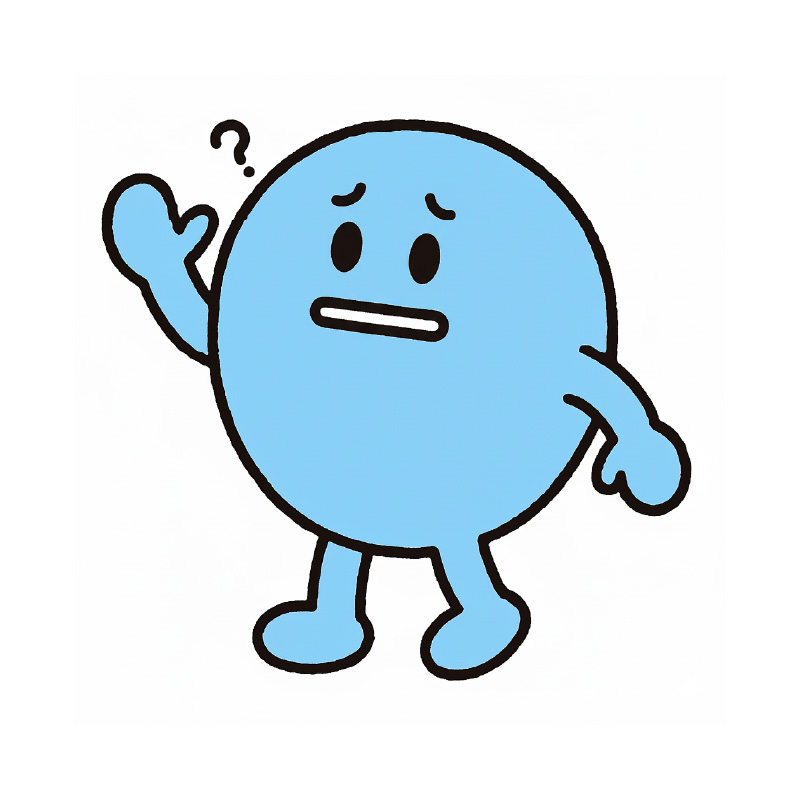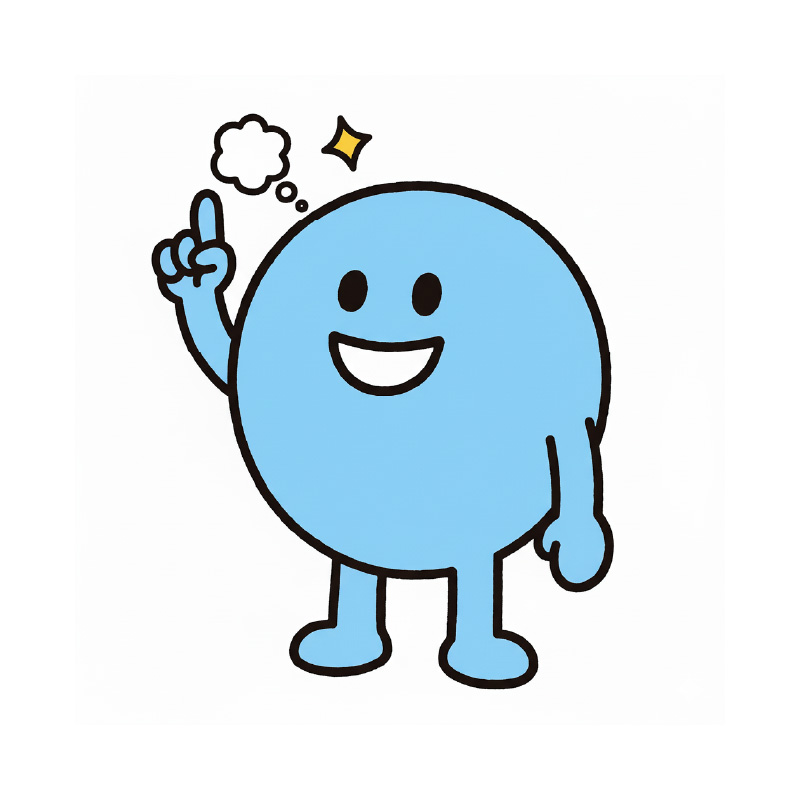基礎からわかる解説シリーズ
ウェブ版のバリアフリー:みんなのための基本ルール
連載スタート!全5回でわかるウェブアクセシビリティ
今回から全5回にわたり、「ウェブアクセシビリティ」についてわかりやすく解説する連載をお届けします。
第1回では、そもそも「ウェブアクセシビリティとは何か?」という基本から、私たちが日常的に使っているウェブサイトにどう関わってくるのかを見ていきます。
ウェブアクセシビリティとは?
スピリッツ君とアクセスくんの会話(第2章)
近年、ウェブアクセシビリティという言葉を目にする機会が増えてきました。
一言でいえば、どんな人でも同じようにウェブサイトやアプリなどを使えるようにする取り組みのことです。
これは、現実の世界のバリアフリーをインターネットの世界で実現する考え方です。
たとえば、車椅子の人が建物に入るためにスロープがあるように、ウェブ上でも、操作が難しいデザインや、見づらい文字、読み上げに対応していない構造など、さまざまなデジタルのバリア(障壁)があります。
それを取り除いていく考え方です。
年齢、目の見え方、聞こえ方、マウスが使えない人、使うデバイス(パソコン・スマートフォン)、ネット環境など、利用者の状況は実にさまざま。ウェブアクセシビリティは、こうした多様性を前提に、誰にとっても情報が届き、スムーズに使えるようにする思いやりのある設計なのです。
誰にとっても「使いやすい」ってどういうこと?
スピリッツ君とアクセスくんの会話(第3章)
ウェブアクセシビリティというと、障害のある人のためのものと思われがちです。
でも、実はもっと広い視点で考えることができます。
たとえば、
- 色のコントラストが弱くて文字が読みにくい
- 小さな文字が拡大できない
- ボタンが小さくて押しづらい
こうしたことは、特別な障害がなくても誰にでも起こります。
また、身体の状態や周囲の環境によって、一時的に困ることもあります。
- 加齢や目の疲れが原因で細かい文字が読みづらい
- 視覚に障害がなくても、晴れた日にスマホ画面がまぶしく見えにくい
- けがをしてしまい、一時的に片手が使えない
- 電車の中で音を出せない
- 通信が遅く、画像が表示されにくい
このように使いにくさは、特定の人だけの問題ではなく、私たち全員に起こりうることなのです。
「みんなにやさしいウェブ」って、どんな考え方?
スピリッツ君とアクセスくんの会話(第4章)
前の章で見たように、使いにくさは誰にでも起こり得るものです。
では、そうした困りごとを減らすにはどうすればよいのでしょうか。
その答えが、みんなにやさしい設計―アクセシビリティの考え方です。
たとえば建物のスロープは、車椅子の人のためだけではありません。ベビーカーを押す人や、大きな荷物を持っている人にも便利です。
ウェブでも同じように、誰かのための配慮は結果的にすべての人にとっての使いやすさにつながります。
色の見やすさ、文字の大きさ、操作しやすいボタン、わかりやすい構造などがそれに当たります。
アクセシビリティの改善は特別な対応ではなく、誰もが快適に使えるウェブを作るための基本姿勢です。
この考え方こそが「みんなにやさしいウェブ」です。
実は「特別なこと」ではありません
スピリッツ君とアクセスくんの会話(第5章)
みんなにやさしいウェブを実現するためには、 確かに専門的な知識や仕組みが必要になる場面もあります。ただ、最初の一歩は特別な技術からではなく、身近なところから始められるのです。
1.文字に十分な大きさとコントラストをつける
目の不自由な方、高齢者、まぶしい屋外でスマホを使う人にやさしくできます。
小さな文字や、背景と文字の色の差が少ないデザインは、内容が読みづらくなってしまいます。
たとえば、白い文字を薄い色の背景に重ねると見えにくくなりますが、文字を大きくしたり、背景との色の差をはっきりさせるだけでも読みやすくなります。
2.画像には代替テキスト(alt属性)を入れる
目の見えない方や画像が表示されない環境でも内容が伝わります。
「alt属性(オルト属性)」とは、画像の内容を説明する代わりのテキストのことです。
たとえば、画面を読み上げる機械(スクリーンリーダー)は、「alt属性」に何も書かれていなければ、「画像があります」としか読むことができません。
そこで、「alt属性」に「夕焼け空をバックに笑っている子どもが手をつないでいる」といった説明を入れることで、画像の意味や雰囲気まで伝えられるのです。
3.リンクやボタンには「何をするのか」が分かるリンクテキストをつける。
マウスを使わない人やスクリーンリーダーを使う人、また急いで操作している人にも分かりやすくなります。
リンクやボタンの文字がここをクリックやもっと見るだけだと、どこへ進むのか、何が起こるのかが分かりません。
なので「製品カタログ(PDF)をダウンロード」のように、行き先や操作内容を具体的に書くことで、ページの名前やどんな操作なのかが伝わり、より分かりやすくなります。
ウェブアクセシビリティは完璧にするか・しないかではなく、少しずつ良くしていくことが大切です。
小さな配慮を重ねていくことが、最終的に多くの人にやさしいウェブにつながります

今回のまとめ
スピリッツ君とアクセスくんの会話(第6章)
ウェブアクセシビリティとは、すべての人が必要な情報をちゃんと届けるようにするための基本的な考え方です。
それは特別な取り組みではなく、思いやりを形にするウェブ版のバリアフリーで、誰もが使いやすいウェブサイトへの第一歩なのです。
次回は、なぜウェブアクセシビリティを向上させる必要があるのかについて、その背景にある社会の変化や、多様な利用者の視点から考えていきます。
出典:政府広報オンライン「誰もが利用しやすいウェブサイトに(ウェブアクセシビリティ)」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202310/2.html(外部リンク)