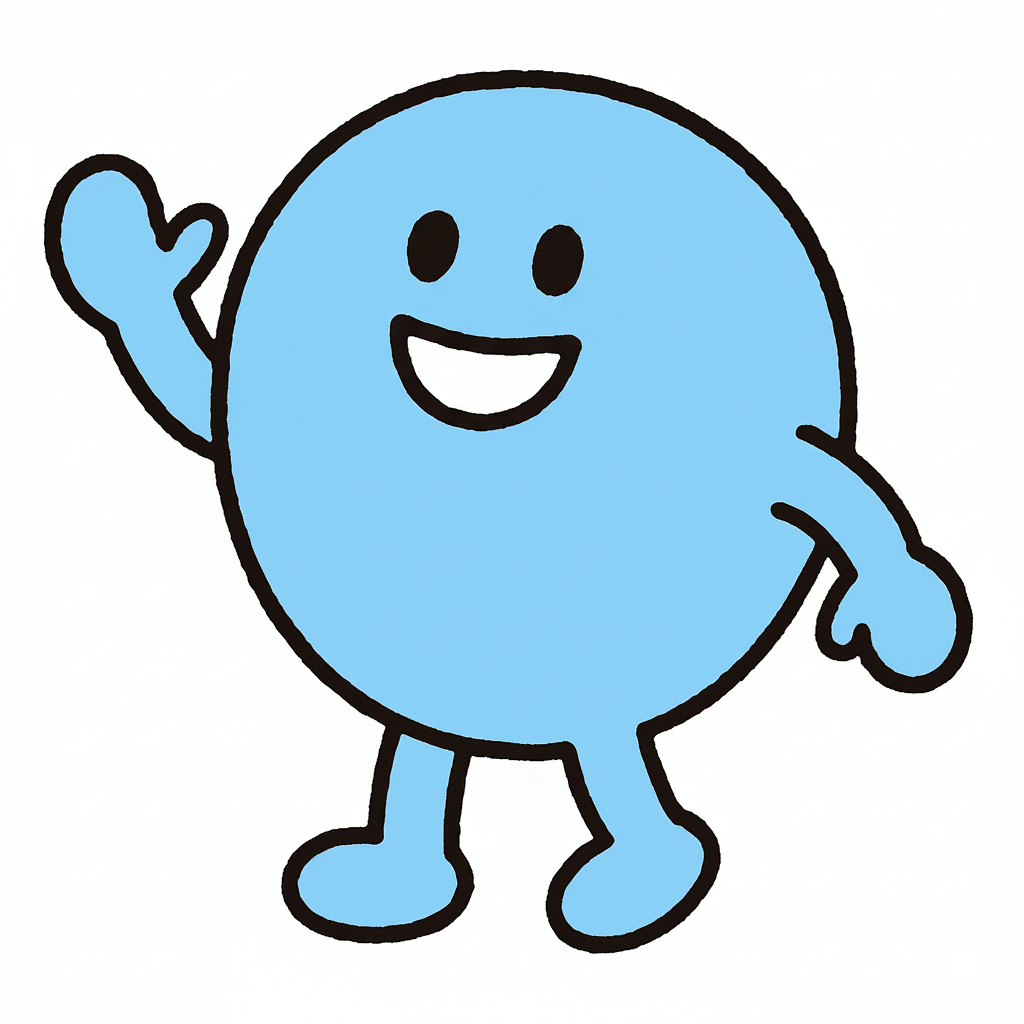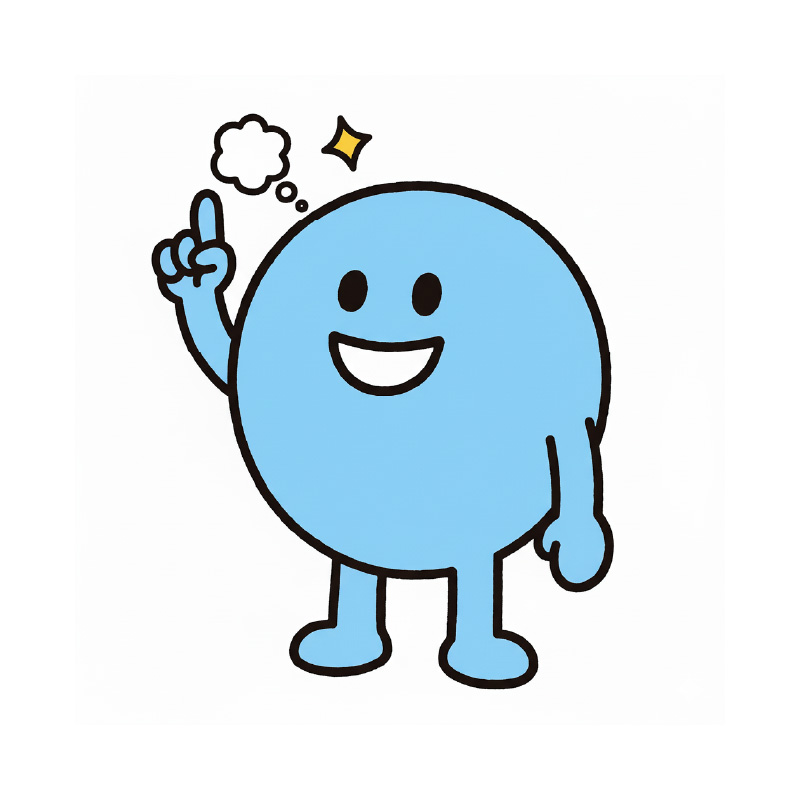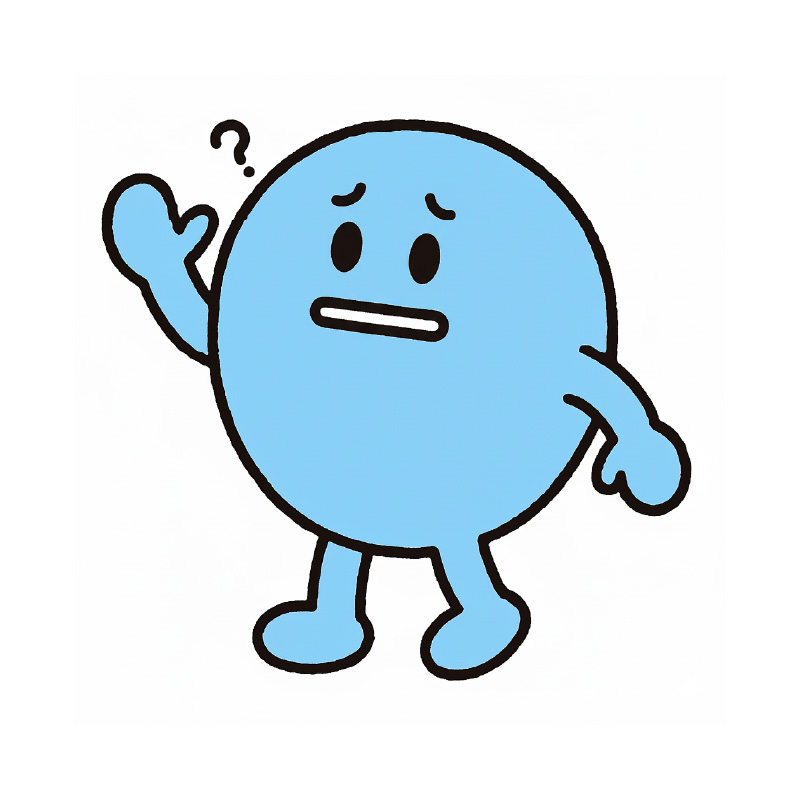基礎からわかる解説シリーズ
ウェブは社会のインフラになっている
スピリッツ君とアクセスくんの会話(第1章)
いま、ウェブサイトは生活のあらゆる場面に欠かせない存在になっています。
ニュースを読んだり、商品を買ったり、行政の手続きをしたり、学校の授業を受けたり─。
年齢や地域を問わず、多くの人がスマートフォンやパソコン、タブレットなどさまざまなデバイスで日常的にウェブを利用しています。
つまりウェブは、電気や水道と同じように、社会を支えるインフラのひとつになっているのです。
だからこそ、すべての人が安心して使えることが前提でなければなりません。
しかし、もしウェブサイトがアクセシビリティに配慮されていなければ、必要な情報にたどりつけない人が出てきます。
こうした差が積み重なると、情報格差(デジタル・ディバイド)が生まれます。
情報格差がもたらす社会的な不利益
スピリッツ君とアクセスくんの会話(第2章)
情報格差(デジタル・ディバイド)は、単なる「不便」ではなく、教育・雇用・行政サービスなど、社会生活そのものに影響を及ぼす問題です。
障害や加齢による身体的な制約だけでなく、経済的な事情で新しい機器を持てない人や、通信環境が整っていない地域に住む人など、アクセスが制限される理由はさまざまです。
たとえば、就職や入学の申し込みがオンラインのみで行われる場合、必要な情報にアクセスできない人はその機会を失ってしまいます。
また、災害時に避難場所や支援情報をウェブで得られない状況になれば、生命に関わる危険に直面することもあります。
つまり、ウェブアクセシビリティの確保は、「誰でも情報にアクセスできるようにする」ための思いやりにとどまらず、社会の公平性と安全を守るための取り組みなのです。

アクセシビリティが確保されたウェブとは?
スピリッツ君とアクセスくんの会話(第3章)
- 目が見えなくても内容が伝わる(読み上げに対応している)
- マウスが使えなくてもキーボードで操作できる
- 色の見え方が違っても情報が欠けない
- 音声が聞こえなくても字幕などで内容を理解できる
こうした配慮は、障害のある人だけでなく、一時的に手が使えない人や、まぶしい屋外でスマホを操作する人など、誰にとっても「使いやすさ」を高めます。
そして、こうした取り組みを支える国際的な基準が、WCAG(Web Content Accessibility Guidelines) です。
ここでは、アクセシブルなウェブを作るための4つの基本原則が定められています。
今回はその四原則を簡単に紹介し、次回で詳しく見ていきます。
- 知覚可能(Perceivable):情報を見たり、聞いたりして得られる
- 操作可能(Operable):誰でも操作できる
- 理解可能(Understandable):内容がわかりやすい
- 堅牢(Robust):さまざまな環境で正しく動作する
これらの4つの原則が、アクセシブルなウェブの土台となります。
この4原則が満たされることで、私たちの日常のウェブ利用がどんなふうに便利になるのかを、第3回で詳しく紹介します。
アクセシビリティは義務から責任へ
2024年4月に施行された改正障害者差別解消法により、民間企業にも「合理的配慮の提供」が義務化されました。
これにより、アクセシビリティは個々の努力ではなく、社会全体の責任として求められるようになったのです。
ただちにすべてのウェブサイトがJISやWCAGといった基準への完全な対応が義務化されたわけではありませんが、行政や企業の方針としてこれらの基準に沿った改善を進めることが強く推奨されています。
スピリッツ君とアクセスくんの会話(第4章)
今回のまとめ
ウェブアクセシビリティは、「一部の人のための工夫」ではなく、社会全体がつながり続けるための基礎です。
ウェブが生活のインフラとなった今、アクセシビリティを欠いた設計は、情報格差を広げ、教育や雇用、日常生活の中で不平等を生む原因になります。
逆に、アクセシビリティを整えることは、誰もが同じように情報を受け取り、サービスを利用できる社会をつくることです。
それは、技術だけでなく思いやりを形にする社会の仕組みなのです。
次回(第3回)は、この4原則が満たされることで、私たちのウェブサイトでの体験がどのように便利でやさしくなるのかを、利用者の視点から具体的に見ていきます。
出典:政府広報オンライン「誰もが利用しやすいウェブサイトに(ウェブアクセシビリティ)」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202310/2.html(外部リンク)
全5回でわかるウェブアクセシビリティ連載
- 第1回 ウェブアクセシビリティとは?
- 第2回 なぜウェブアクセシビリティを向上させる必要があるのか(本ページ)
- 第3回 ウェブアクセシビリティが確保されたウェブサイトはどんなふうに便利?
- 第4回 実践!ウェブアクセシビリティを高める基本チェック項目
- 第5回 すべての人がアクセスできる社会を目指して